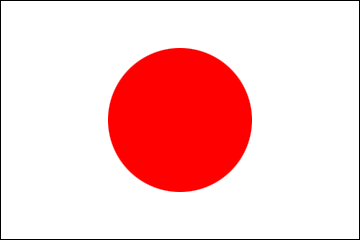領事窓口業務(旅券・査証・各種証明・在外選挙等)2024年4月
令和6年5月1日
旅券(パスポート)
在コンゴ民主共和国日本大使館では、旅券に関する事務を行っております。申請手続きに通常必要な書類の詳細については、外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html)をご覧下さい。
1.新規発給
(1)申請理由
・初めて旅券を申請する方
・旅券の有効期限が既に切れている方
・旅券を紛失・盗難・焼失し、紛焼失届を提出して新たに申請する方
・氏名や本籍地の都道府県等記載事項に変更のある方(変更前の旅券と有効期間満了日が同一である記載事項変更旅券も可能です。)
(2)必要書類
・一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
18歳以上の方(申請日現在)は10年用と5年用のいずれかのパスポートを選択できますが、18歳未満の方は5年用のみとなります。
国外では併せて「ダウンロード申請書」が使用できます。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
・戸籍謄本 1通
申請日前6か月以内に発行されたもので、原本を必要とします。
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
6か月以内に撮影されたもので、カラー・白黒は問いません。
・有効旅券(現在所持している旅券)
・コンゴ(民)滞在許可証(呈示のみ)
※ 国際結婚又は両親のいずれかが外国籍である等の理由で、非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合は、出生証明書など外国政府機関が発行した氏名の綴りが確認のできる書類が必要です。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_002789.html)
※ 原則として、申請は本人が出頭することが原則です。但し、未成年(18歳未満)の場合には、親などの法定代理人による代理申請が可能です。その場合は、予め所定の申請用紙を当大使館にて入手して頂き、申請人本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が持参して下さい。なお、受領に関しては、必ず本人出頭が必要です。
2.切替申請
(1)申請理由
・残存有効期間が1年未満となった場合
(2)必要書類
・一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
18歳以上の方(申請日現在)は10年用と5年用のいずれかのパスポートを選択できますが、18歳未満の方は5年用のみとなります。
国外では併せて「ダウンロード申請書」が使用できます。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
6か月以内に撮影されたもので、カラー・白黒は問いません。
・有効旅券(現在所持している旅券)
返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期限には加算されません。
・戸籍謄本 1通(戸籍上の身分事項に変更がある場合)
申請日前6か月以内に発行されたもので、原本を必要とします。
3.氏名や本籍等の変更
(1)申請理由
・結婚や養子縁組等により、お名前に変更があった場合
・本籍地の都道府県に変更があった場合
・国際結婚等で、外国の氏名等を別名として追記または削除する場合
(2)必要書類
・一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通
国外では併せて「ダウンロード申請書」が使用できます。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
・旅券の記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本 1通
申請日前6か月以内に発行されたもので、原本を必要とします。
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
6か月以内に撮影されたもので、カラー・白黒は問いません。
・有効旅券
返納していただき、失効処理をいたします。返納した旅券と有効期間満了日が同一の旅券を新たに発行します。
・コンゴ(民)滞在許可証(提示)
外国人夫の姓の併記を希望する場合は、IDカード等、綴りの確認ができる書類
4.査証欄の増補
注)改正旅券法が施行された令和5年3月27日以降、査証欄の増補制度が廃止されました。
5.紛失届
(1)申請理由
旅券を紛失、盗難、焼失された場合
(2)必要書類
・紛失一般旅券等届出書 1通
国外では併せて「ダウンロード申請書」が使用できます。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
・警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
6か月以内に撮影されたもので、カラー・白黒は問いません。
・その他参考となる書類(必要に応じ、本人確認、国籍確認ができるもの)
(3)新たな旅券(又は帰国のための渡航書)の取得のため、上記の書類に加え以下の書類が必要になります。
(新規旅券を申請する場合)
・一般旅券発給申請書(10年用又は5年用)1通
・戸籍謄本 1通
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
(渡航書を申請する場合)
・渡航書発給申請書 1通
・戸籍謄本(原本を必要とします)1通 又は日本国籍があることを確認できる書類
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
・その他日程等が確認できる書類
6.パスポート用写真について
・申請者(請求者)本人のみが撮影されたもの
・提出日前6ヶ月以内に撮影されたもの
・縦45ミリメートル×横35ミリメートル
・無帽で正面を向いたもの
・背景(影を含む)がないもの
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html)
7.旅券手数料
2024年4月1日現在の旅券手数料は、下記の通りです。
・一般旅券 (10年有効)の発給: 254,000FC
・一般旅券 (5年有効)の発給: 174,600FC
・一般旅券 (12歳未満・5年有効)の発給: 95,200FC
・帰国のための渡航書の発給: 39,700FC
在コンゴ民主共和国日本大使館では、旅券に関する事務を行っております。申請手続きに通常必要な書類の詳細については、外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html)をご覧下さい。
1.新規発給
(1)申請理由
・初めて旅券を申請する方
・旅券の有効期限が既に切れている方
・旅券を紛失・盗難・焼失し、紛焼失届を提出して新たに申請する方
・氏名や本籍地の都道府県等記載事項に変更のある方(変更前の旅券と有効期間満了日が同一である記載事項変更旅券も可能です。)
(2)必要書類
・一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
18歳以上の方(申請日現在)は10年用と5年用のいずれかのパスポートを選択できますが、18歳未満の方は5年用のみとなります。
国外では併せて「ダウンロード申請書」が使用できます。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
・戸籍謄本 1通
申請日前6か月以内に発行されたもので、原本を必要とします。
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
6か月以内に撮影されたもので、カラー・白黒は問いません。
・有効旅券(現在所持している旅券)
・コンゴ(民)滞在許可証(呈示のみ)
※ 国際結婚又は両親のいずれかが外国籍である等の理由で、非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合は、出生証明書など外国政府機関が発行した氏名の綴りが確認のできる書類が必要です。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_002789.html)
※ 原則として、申請は本人が出頭することが原則です。但し、未成年(18歳未満)の場合には、親などの法定代理人による代理申請が可能です。その場合は、予め所定の申請用紙を当大使館にて入手して頂き、申請人本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が持参して下さい。なお、受領に関しては、必ず本人出頭が必要です。
2.切替申請
(1)申請理由
・残存有効期間が1年未満となった場合
(2)必要書類
・一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
18歳以上の方(申請日現在)は10年用と5年用のいずれかのパスポートを選択できますが、18歳未満の方は5年用のみとなります。
国外では併せて「ダウンロード申請書」が使用できます。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
6か月以内に撮影されたもので、カラー・白黒は問いません。
・有効旅券(現在所持している旅券)
返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期限には加算されません。
・戸籍謄本 1通(戸籍上の身分事項に変更がある場合)
申請日前6か月以内に発行されたもので、原本を必要とします。
3.氏名や本籍等の変更
(1)申請理由
・結婚や養子縁組等により、お名前に変更があった場合
・本籍地の都道府県に変更があった場合
・国際結婚等で、外国の氏名等を別名として追記または削除する場合
(2)必要書類
・一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通
国外では併せて「ダウンロード申請書」が使用できます。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
・旅券の記載に変更を生じたことが確認できる戸籍謄本 1通
申請日前6か月以内に発行されたもので、原本を必要とします。
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
6か月以内に撮影されたもので、カラー・白黒は問いません。
・有効旅券
返納していただき、失効処理をいたします。返納した旅券と有効期間満了日が同一の旅券を新たに発行します。
・コンゴ(民)滞在許可証(提示)
外国人夫の姓の併記を希望する場合は、IDカード等、綴りの確認ができる書類
4.査証欄の増補
注)改正旅券法が施行された令和5年3月27日以降、査証欄の増補制度が廃止されました。
5.紛失届
(1)申請理由
旅券を紛失、盗難、焼失された場合
(2)必要書類
・紛失一般旅券等届出書 1通
国外では併せて「ダウンロード申請書」が使用できます。
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
・警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
6か月以内に撮影されたもので、カラー・白黒は問いません。
・その他参考となる書類(必要に応じ、本人確認、国籍確認ができるもの)
(3)新たな旅券(又は帰国のための渡航書)の取得のため、上記の書類に加え以下の書類が必要になります。
(新規旅券を申請する場合)
・一般旅券発給申請書(10年用又は5年用)1通
・戸籍謄本 1通
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
(渡航書を申請する場合)
・渡航書発給申請書 1通
・戸籍謄本(原本を必要とします)1通 又は日本国籍があることを確認できる書類
・写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
・その他日程等が確認できる書類
6.パスポート用写真について
・申請者(請求者)本人のみが撮影されたもの
・提出日前6ヶ月以内に撮影されたもの
・縦45ミリメートル×横35ミリメートル
・無帽で正面を向いたもの
・背景(影を含む)がないもの
詳細は、以下の外務省ホームページをご覧ください。(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html)
7.旅券手数料
2024年4月1日現在の旅券手数料は、下記の通りです。
・一般旅券 (10年有効)の発給: 254,000FC
・一般旅券 (5年有効)の発給: 174,600FC
・一般旅券 (12歳未満・5年有効)の発給: 95,200FC
・帰国のための渡航書の発給: 39,700FC
在コンゴ民主共和国日本大使館では、旅券に関する事務を行っております。申請手続きに通常必要な書類の詳細については、外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html)をご覧下さい。
各種届出・証明
1.戸籍・国籍関係
在コンゴ民主共和国日本大使館では、戸籍・国籍に関する事務を行っております。戸籍・国籍関係の詳細については、外務省ホームページ( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html )をご覧下さい。
2.在留届(3か月以上滞在される方へ )
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)サイトから在留届を提出してください。届出者自らが在留届の変更等の手続を行うことができる非常に便利なシステムですので、是非このシステムをご利用願います。
「在留届」を提出いただくことにより、緊急事態が発生した場合には、大使館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられます。なお、海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。 現在、外国にお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。
なお、在留届は書面で提出することも可能ですが、書面によって在留届を提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、管轄の在外公館に書面で変更届又は帰国・転出届を提出していただく必要があります
在留届用紙のダウンロード(PDF)
変更届用紙のダウンロード(PDF)
帰国・転出届用紙のダウンロード(PDF)
3.各種証明
在コンゴ民主共和国大使館では各種証明書の発給を行っておりますが、主要な証明は次の通りです。
(1)印章の証明
日本の公文書を海外で使用するためには、日本の公文書に大使館による認証を要求する場合があります。その場合には、大使館では日本の公文書上に押印された公印について、印章の証明書を発給しています。
(2)翻訳証明
日本の公文書について、提出先の関係機関より、大使館による翻訳証明が要求される場合がありますが、その際は、申請者が翻訳文を作成し、大使館はその翻訳文が正しいことを証明します。
(3)身分上の事項に関する証明
出生、婚姻、死亡、独身であること等身分上の事項について、関係機関より、戸籍謄本等の提示ではなく、大使館によって作成された証明書の提示を要求される場合があります。その際は出生証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書あるいは戸籍記載事項証明書を発給しています。必要書類は基本的に戸籍謄(抄)本です。
(4)在留証明
コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国で生活する日本人が、日本の年金事務所や生命保険会社に年金の請求をしたり、日本の法務局へ不動産の登記をする際など、それら機関に現住所や住所の変更を証明する必要が生じます。その際は、申請者がコンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に在留していることを証明する在留証明書を発給します。
この証明を申請する際に留意すべき点は次の通りです。
(イ) 基本的に現地に3か月以上滞在している必要があります。
(ロ) 原則としてご本人が在コンゴ民主共和国日本大使館(以下、大使館)に出向いていただく必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には、代理の方を通じて申請・受領ができます。その場合には委任状が必要となります。
(ハ) 現地の官公署が発行した、現住所(必要な場合は過去の住所)を証明する文書を、大使館で提示してもらう必要があります。例えば、住所が記載された納税証明書、電気・ガス等の公共料金の領収書、現地の運転免許証、現地の警察が発行した居住証明等です。
(ニ) 不動産登記の際は現住所の他に過去の住所の証明も必要になる場合がありますが、大使館では現地官公署の発行した証拠文書に基づく範囲でしか証明できません。証拠文書がない場合には上申書を提出先に提示することになります。公文書にする必要があると言われた場合は、日本の公証人に署名証書を作成してもらうことになります。一旦、日本に帰国すれば在留証明書は発給されません。あくまで現にコンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に住所を有して、コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に在住する方に対してのみ発給されます。日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には、納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の入国管理当局による出入国印等を、直接国内関係機関に提示することになります。勤務先の会社による在外勤務証明書を提示することでもよいかもしれません。提出先によく相談して下さい。どうしても公文書による必要があれば、日本の公証人に署名証書を作成してもらうことになります。
(ホ) お名前を漢字あるいは仮名のつづりで記載する必要がありますので、戸籍謄(抄)本を大使館に提示していただきます。
(5)署名証明
日本では不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等に、印鑑証明が必要になる場合があります。
しかし、日本に住民登録がなければ日本の官公署で印鑑登録ができません。そのため法務局や銀行等では、日本に住民登録のない海外在留日本人のために、印鑑証明に代わるものとして、大使館による署名証明の提示があれば受け付けてくれます。
この場合、海外在留日本人より申請があれば大使館では署名証明を行います(銀行等、提出先より拇印証明が要求されている旨のご説明があれば、拇印証明も併せて行います)。領事担当官の面前で署名する必要がありますので、申請者は大使館に直接出向く必要があります。
なお、公館では署名を証明する一枚紙の署名証明書を作成するのみで、その署名と署名すべき文書の署名との照合は、法務局等提出先が行う形式と、署名すべき別添文書の署名も領事の面前で行い、署名証明書と別添文書の間を割り印し、署名証明書と別添文書を併せて一つの証明書とする形式との2つの形式がありますが、どちらにするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に確認の上、申請する必要があります。
大使館が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありませんので、本件署名証明は、あくまで海外在留日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに行うものであることに留意願います。
(6)警察証明
長期ビザ等の申請をする際など、関係機関より無犯罪歴証明書の提示を要求される場合があります。日本に在住する者に対しては、都道府県警が対応しますが、コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に在留する者については、大使館に申請がなされれば、警察庁で申請理由等を検討の上、警察証明書が発給されます。発給された警察証明書は大使館より申請者に手交されます。申請の際に、大使館で指紋原紙に指紋を採取しますので、申請者が直接大使館に出向く必要があります(手数料無料)。
※大使館にて申請された場合、発給された警察証明書が手元に届けられるまで、通常約2ヶ月程度必要となりますので、長期ビザ等の申請で事前に警察証明書が必要である場合、日本で手続きを済ませておかれることをお薦め致します。
4.各種証明手数料
2024年4月1日現在の主要な各種証明手数料は、下記の通りです。
・署名又は印章の証明: 71,400FC(官公署に係るもの)/27,000FC(その他のもの)
・翻訳証明: 69,800FC
・出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明: 19,000FC
・在留証明 : 19,000FC
在コンゴ民主共和国日本大使館では、戸籍・国籍に関する事務を行っております。戸籍・国籍関係の詳細については、外務省ホームページ( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html )をご覧下さい。
2.在留届(3か月以上滞在される方へ )
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、「在留届電子届出システム(ORRnet)サイトから在留届を提出してください。届出者自らが在留届の変更等の手続を行うことができる非常に便利なシステムですので、是非このシステムをご利用願います。
「在留届」を提出いただくことにより、緊急事態が発生した場合には、大使館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられます。なお、海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。 現在、外国にお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。
なお、在留届は書面で提出することも可能ですが、書面によって在留届を提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、管轄の在外公館に書面で変更届又は帰国・転出届を提出していただく必要があります
在留届用紙のダウンロード(PDF)
変更届用紙のダウンロード(PDF)
帰国・転出届用紙のダウンロード(PDF)
3.各種証明
在コンゴ民主共和国大使館では各種証明書の発給を行っておりますが、主要な証明は次の通りです。
(1)印章の証明
日本の公文書を海外で使用するためには、日本の公文書に大使館による認証を要求する場合があります。その場合には、大使館では日本の公文書上に押印された公印について、印章の証明書を発給しています。
(2)翻訳証明
日本の公文書について、提出先の関係機関より、大使館による翻訳証明が要求される場合がありますが、その際は、申請者が翻訳文を作成し、大使館はその翻訳文が正しいことを証明します。
(3)身分上の事項に関する証明
出生、婚姻、死亡、独身であること等身分上の事項について、関係機関より、戸籍謄本等の提示ではなく、大使館によって作成された証明書の提示を要求される場合があります。その際は出生証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書あるいは戸籍記載事項証明書を発給しています。必要書類は基本的に戸籍謄(抄)本です。
(4)在留証明
コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国で生活する日本人が、日本の年金事務所や生命保険会社に年金の請求をしたり、日本の法務局へ不動産の登記をする際など、それら機関に現住所や住所の変更を証明する必要が生じます。その際は、申請者がコンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に在留していることを証明する在留証明書を発給します。
この証明を申請する際に留意すべき点は次の通りです。
(イ) 基本的に現地に3か月以上滞在している必要があります。
(ロ) 原則としてご本人が在コンゴ民主共和国日本大使館(以下、大使館)に出向いていただく必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には、代理の方を通じて申請・受領ができます。その場合には委任状が必要となります。
(ハ) 現地の官公署が発行した、現住所(必要な場合は過去の住所)を証明する文書を、大使館で提示してもらう必要があります。例えば、住所が記載された納税証明書、電気・ガス等の公共料金の領収書、現地の運転免許証、現地の警察が発行した居住証明等です。
(ニ) 不動産登記の際は現住所の他に過去の住所の証明も必要になる場合がありますが、大使館では現地官公署の発行した証拠文書に基づく範囲でしか証明できません。証拠文書がない場合には上申書を提出先に提示することになります。公文書にする必要があると言われた場合は、日本の公証人に署名証書を作成してもらうことになります。一旦、日本に帰国すれば在留証明書は発給されません。あくまで現にコンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に住所を有して、コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に在住する方に対してのみ発給されます。日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には、納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の入国管理当局による出入国印等を、直接国内関係機関に提示することになります。勤務先の会社による在外勤務証明書を提示することでもよいかもしれません。提出先によく相談して下さい。どうしても公文書による必要があれば、日本の公証人に署名証書を作成してもらうことになります。
(ホ) お名前を漢字あるいは仮名のつづりで記載する必要がありますので、戸籍謄(抄)本を大使館に提示していただきます。
(5)署名証明
日本では不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等に、印鑑証明が必要になる場合があります。
しかし、日本に住民登録がなければ日本の官公署で印鑑登録ができません。そのため法務局や銀行等では、日本に住民登録のない海外在留日本人のために、印鑑証明に代わるものとして、大使館による署名証明の提示があれば受け付けてくれます。
この場合、海外在留日本人より申請があれば大使館では署名証明を行います(銀行等、提出先より拇印証明が要求されている旨のご説明があれば、拇印証明も併せて行います)。領事担当官の面前で署名する必要がありますので、申請者は大使館に直接出向く必要があります。
なお、公館では署名を証明する一枚紙の署名証明書を作成するのみで、その署名と署名すべき文書の署名との照合は、法務局等提出先が行う形式と、署名すべき別添文書の署名も領事の面前で行い、署名証明書と別添文書の間を割り印し、署名証明書と別添文書を併せて一つの証明書とする形式との2つの形式がありますが、どちらにするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に確認の上、申請する必要があります。
大使館が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありませんので、本件署名証明は、あくまで海外在留日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに行うものであることに留意願います。
(6)警察証明
長期ビザ等の申請をする際など、関係機関より無犯罪歴証明書の提示を要求される場合があります。日本に在住する者に対しては、都道府県警が対応しますが、コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に在留する者については、大使館に申請がなされれば、警察庁で申請理由等を検討の上、警察証明書が発給されます。発給された警察証明書は大使館より申請者に手交されます。申請の際に、大使館で指紋原紙に指紋を採取しますので、申請者が直接大使館に出向く必要があります(手数料無料)。
※大使館にて申請された場合、発給された警察証明書が手元に届けられるまで、通常約2ヶ月程度必要となりますので、長期ビザ等の申請で事前に警察証明書が必要である場合、日本で手続きを済ませておかれることをお薦め致します。
4.各種証明手数料
2024年4月1日現在の主要な各種証明手数料は、下記の通りです。
・署名又は印章の証明: 71,400FC(官公署に係るもの)/27,000FC(その他のもの)
・翻訳証明: 69,800FC
・出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明: 19,000FC
・在留証明 : 19,000FC
在外選挙
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に居住する皆様の在外選挙人名簿への登録の申請は、の在コンゴ民主共和国日本大使館の領事窓口で受け付けています。登録されるためには、大使館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
1.在外投票の方法
(1)在外公館投票
在コンゴ民主共和国日本大使館では、在外公館投票を行うことができます。
(2)郵便投票
在外公館等で投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館から住所地が遠隔の地にある場合には、郵便による投票もできます。
※ 郵便による投票の仕方
外選挙人は、在外選挙人が登録されている市町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封し投票用紙を請求する。市町村選挙管理委員会から在外選挙人証が返送され投票用紙が届いたら投票用紙に記入し市町村選挙委員会に郵送する。
(3)帰国投票
また、在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票することができます。
2.海外で選挙権を行使するために
(1)在外選挙人名簿への登録
在外投票をするには先ず、在コンゴ民主共和国日本大使館で在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。申請により在外選挙人名簿に登録されると、在外投票ができることとなり、投票の時に必要な「在外選挙人証」が所定の市町村選挙管理委員会から在コンゴ民主共和国日本大使館を通じて交付されます。
(2)登録資格
年齢満18年以上(平成28年6月19日、改正公職選挙法施行)の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)で、引き続き3か月以上コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に住所を有する方
※ 転出届が未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合があります。
(3)申請方法
申請者本人が必ず大使館の領事窓口に行って申請して下さい。申請書は大使館にあります。
(4)在外選挙人名簿の登録市町村
原則として、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会です。
(5)登録申請の時に持参するもの
次の2種類の書類を必ずお持ち下さい。
・現在の有効な旅券
・3か月以上コンゴ民主共和国又はコンゴ共和国に住所を有することを証明する書類
※ 在留届を大使館に3か月以上前に提出している場合は不要です。
(6)在外選挙の対象となる選挙
・衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙
・衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙、これらに関わる補欠選挙及び再選挙
・国民投票
(7)選挙できる選挙区
登録された市町村の属する選挙区となります。
在外選挙の詳細については、外務省ホームページ( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html )をご覧下さい。
コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に居住する皆様の在外選挙人名簿への登録の申請は、の在コンゴ民主共和国日本大使館の領事窓口で受け付けています。登録されるためには、大使館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
1.在外投票の方法
(1)在外公館投票
在コンゴ民主共和国日本大使館では、在外公館投票を行うことができます。
(2)郵便投票
在外公館等で投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館から住所地が遠隔の地にある場合には、郵便による投票もできます。
※ 郵便による投票の仕方
外選挙人は、在外選挙人が登録されている市町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封し投票用紙を請求する。市町村選挙管理委員会から在外選挙人証が返送され投票用紙が届いたら投票用紙に記入し市町村選挙委員会に郵送する。
(3)帰国投票
また、在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票することができます。
2.海外で選挙権を行使するために
(1)在外選挙人名簿への登録
在外投票をするには先ず、在コンゴ民主共和国日本大使館で在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。申請により在外選挙人名簿に登録されると、在外投票ができることとなり、投票の時に必要な「在外選挙人証」が所定の市町村選挙管理委員会から在コンゴ民主共和国日本大使館を通じて交付されます。
(2)登録資格
年齢満18年以上(平成28年6月19日、改正公職選挙法施行)の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)で、引き続き3か月以上コンゴ民主共和国及びコンゴ共和国に住所を有する方
※ 転出届が未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合があります。
(3)申請方法
申請者本人が必ず大使館の領事窓口に行って申請して下さい。申請書は大使館にあります。
(4)在外選挙人名簿の登録市町村
原則として、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会です。
(5)登録申請の時に持参するもの
次の2種類の書類を必ずお持ち下さい。
・現在の有効な旅券
・3か月以上コンゴ民主共和国又はコンゴ共和国に住所を有することを証明する書類
※ 在留届を大使館に3か月以上前に提出している場合は不要です。
(6)在外選挙の対象となる選挙
・衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙
・衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙、これらに関わる補欠選挙及び再選挙
・国民投票
(7)選挙できる選挙区
登録された市町村の属する選挙区となります。
在外選挙の詳細については、外務省ホームページ( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html )をご覧下さい。
日本への入国査証(コンゴ民主共和国在住の外国人を日本に招聘する場合など)
(1)在コンゴ民主共和国日本大使館では、日本に入国する際の査証申請の受付及び発給を行っております。
査証申請に関するお問い合わせ:consul.amb@ki.mofa.go.jp(日本語・フランス語対応)
日本国査証案内(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html)
提出書類一覧
(2)査証の原則的発給基準は以下の通りです。
原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われる。
(イ)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(ロ)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(ハ)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。 以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(ニ)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
査証申請に関するお問い合わせ:consul.amb@ki.mofa.go.jp(日本語・フランス語対応)
日本国査証案内(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html)
提出書類一覧
(2)査証の原則的発給基準は以下の通りです。
原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われる。
(イ)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(ロ)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(ハ)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。 以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(ニ)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。