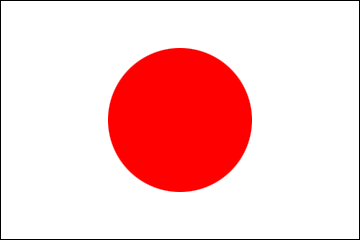現地情報(入国に関する注意事項、首都情報、治安情報等)
入国に関する注意事項
1.査証
コンゴ民主共和国に入国しようとする場合は、あらかじめ駐日コンゴ民主共和国大使館などで査証を取得しておく必要があります。最新の情報については、在京コンゴ民主共和国大使館(住所:東京都港区南青山2-9-21 、電話:03-6456-4394、E-mail:visa@embassyofdrcongo.com)等に確認してください。査証に関する問い合わせはE-mailのみで受け付けております。
入国査証は、申請者の居住国で取得しなければなりません。居住国以外で取得したコンゴ民主共和国の入国査証は、入国時に無効と判断される場合がありますので、ご注意下さい。ただし、居住国にコンゴ民主共和国の大使館が無い場合、コンゴ民主共和国大使館を有する近隣国での取得が認められていますが、事前に当該大使館にご確認下さい。
2.イエローカード
査証取得のためにはイエローカード(黄熱病予防接種証明書)が必要です。また、入国に際してもイエローカードが必要で、もし所持していない場合は、強制的に接種される上、接種代金及び反則金を徴収されます。イエローカードの有効期間は、2016年7月11日以降WHOの決定によって、「接種10日後から10年間」から「接種10日後から生涯有効」へと変更されており、当地の査証取得及び入国の際にも「生涯有効」は適用されております。
3.外貨持込・持出
入国時に外貨を申告する必要はないものの、1万米ドル相当額以上の現金の持ち込みは禁止されています。また、出国時にはコンゴ・フランの持ち出しは禁止されているほか、1万米ドル相当額以上の外貨現金の持ち出しも禁止されていますのでご注意ください。
4.入国手続き
日本を出国する際、顔認証・指紋認証等の自動化ゲートを利用した場合、そのままでは旅券に出国スタンプが押されず、当地入国時に入国審査官から航空券の半券等の確認や様々な説明を求められるなど慎重な審査を強いられる可能性があります。無用なトラブルを避けるため、スタンプを押してもらうことをお勧めします(自動化ゲートを利用した場合、ゲート通過後、ゲート付近に待機している職員等に申し出れば押印してもらえます)。また、当地での入国審査後、旅券を受け取った時点で入国スタンプの押し忘れがないかを確認してください。
首都キンシャサ情報
1.はじめに
(1)キンシャサとは、現地語の「キンサーサ」(集散地または市場の意)がなまったものと言われています。キンシャサ市は北東から南西にかけて流れる雄大なコンゴ川左岸に位置し、人口は、約1,400万人以上(World Population Prospects 2019)とも言われています。在留日本人数は約70人程度です。
(2)年間平均気温は、26.2℃、大体10月から翌5月頃までが雨期で、好天の時は暑さが大変厳しく多湿で、1~2日に1度くらいの割合で、集中的かつ一時的な大雨が降ります。6月から9月までが乾期で、雨はほとんど降りませんが、曇天の日が多く、そのため気温は余り上がりません。また、湿度も一般に低く(65~70%)、比較的過ごしやすい気候が続きます。
(3)キンシャサ市は東西6kmにわたる「6月30日通り」を中心に、官庁、商店、高級住宅等が建ち並び、ゴンベ地区には外国人も多く住んでいます。コンゴ人の多くは、市内南部の広大な地域(通称「シテ」)に住んでいます。
2.注意事項
(1)写真撮影は、軍事施設、空港、大統領府等の地域、建物が撮影禁止の対象と言われていますが、それ以外のところでも、当局から特別な許可をもらっていない場合は、フィルムやカメラの没収、さらには逮捕されることもありますので原則として写真撮影は行わない方が無難です。特に国境に面するコンゴ川については、出入国ポイントではなく、一見周囲に人影が見えずとも、軍や警察が監視している場合がありますので注意が必要です。
(2)当地もマラリア感染地域になっており、当地滞在中もしくは帰国後にマラリア特有の高熱や風邪のような症状がでたらマラリアの可能性もありますので、病院で当国に渡航した旨を伝えてください。当国滞在中に発症した場合には、新型コロナウイルスの症状との見分けが付きにくいため、早期に掛かりつけ医やお近くの病院で診察する必要があります。また、生水は飲まない方が無難です。病院はいくつかありますが、設備は決して十分とは言えないため、重病の場合は、ヨーロッパなどに搬送されて治療を行うことになります。
(3)不急不要な夜間外出等はできる限り控え、お金や貴重品の管理には細心の注意を払うことが望まれます。
(4)出入国の際、イエローカード(黄熱病)を携行する必要があります。
(5)電気は、220v、50Hzで、コンセントの形状はフランスで使用されているものと同じです。電圧変動が激しい時がありますので使用しない電気機器の電源はこまめに切っておくことをお勧めします。
(6)一部のホテル、スーパーにおいては、クレジットカードを使用することができますが、その他の場所では米ドルもしくはコンゴ・フランの現金のみしか使用できません。また、米ドルであっても、受け取ってくれない店も多く、特に旧紙幣は使えないことが多いようです。また、破損している米ドル紙幣や1ドル紙幣は受け取ってくれない店がほとんどですので、米ドルでおつりを貰った際は、破損していないかどうか、1ドル紙幣が混じっていないか確認することが必要です。
(7)大統領の車列などが通過するときは、白バイなどが制止命令を出しますので素直に従い、車を道路の脇に止め、エンジンを切ると同時に携帯電話や無線機の使用は止めて下さい。
(8)夜間外出するときや市内中心部に出入りするときなど身分証明書の提示を求められることがありますので必ず身分証明書を携帯して下さい。
3.一般事情
(1)市内交通機関
(イ)バスやタクシーなどの公共交通機関は利用しないようにお願いします。窃盗、強盗、誘拐事件被害者になるケースが多く報告されています。
(ロ)レンタカー:運転手付きでレンタカーを借りることが可能です。
(2)通信
(イ)インターネット:近年は通信速度が改善され、4G回線のサービスが普及しています。ホテルではWi-Fiを利用することが可能な上、ポケットWi-Fi等のモデムを購入し、携帯電話会社各社のSIMカードを挿入することで、外出先においてもインターネットを利用することが出来ます。一方、建物の密集地や一部屋内では通信状態が不安定になることがあります。また、各社インターネット料金は予告なく改定されることがしばしばありますので、各社販売店での十分な確認が必要です。
(ロ)郵便:郵便局の利用はお勧めできません。国際間の物流や送付は民間でのDHL社やFEDEX社等の利用が主流です。また、当地での引取り時には想像以上に多額の引取料が要求されます。日本との郵便については、早くて、航空便で約7日、船便で2か月かかりますが、かなり遅れたり、届かない場合がありますので、特に小包等の重要なものは託送するか、ヨーロッパで投函する方がよいでしょう。また、当国では、一般に、個別配達は行われておらず私書箱制となっています。
治安・防犯情報
当国では、銃規制があるものの一部地域では銃器を所持した武装集団による殺人、強盗、誘拐などの凶悪な犯罪が発生しているほか、日中でも財布や携帯電話を狙ったスリやひったくり、人が多数集まる場所でも同様の事案が多発しています。
出入国時において、入国審査官が「入国するには○○ドル支払わなければならない。」「鉱物資源や金属を含むお土産品の携行には税金がかかる。」等と言って、根拠のない金銭を要求する事案も報告されています。
また、年間を通じて、デモやストは頻繁に行われており、注意が必要です。
2.防犯の基本的心構え
○ 昼夜を問わず、不必要な外出は避ける。
○ 公共交通機関(バス、タクシー)等は利用しない。
○ 昼夜を問わず、徒歩での外出はしない。
○ 深夜・未明に及ぶ外出はしない。
○ 外出時、必要以外の多額の現金は携行しない。
○ 外出時、財布・貴重品は外部から視認できる方法で携行しない。
○ 車両乗車時は常時施錠し、必ず窓を閉める。
○ 車両乗車時、駐車後も外部から視認できる場所に財布、携帯電話、貴重品を置かない。
○ 車両乗降時は特に狙われている可能性が高いので油断しない。
○ 警察官から停止を求められても降車しない(窓は開けずに対応する)。
○ 警察官から旅券等の提示を求められても手渡さない(窓越しに見せる)。
○ 多くの人、警察、軍隊が集まる場所には近づかない。
○ 突如、人、警察等が集まり出すなど不穏な状況があれば直ちにその場から離脱する。
○ 公共の場所で写真撮影は行わない(特に、軍、警察、空港、政府施設周辺、国境近辺の河川・湖)。
○ 華美な服装や宗教上、不快感を与えるような服装をしない。
○ 万が一犯罪の被害に遭った場合は抵抗しない(生命の安全を最優先)。
3. 防犯のための具体的注意事項
(1)住居
住居の安全性を高めるポイントを幾つか挙げますので参考にして下さい。
○ 侵入防止対策
人が容易に敷地内に侵入できない物理的、心理的工夫をする必要があります。一戸建て住居の場合、出来るだけ塀等を高く(障害物を入れて概ね2.5m以上)し、鉄条網を張り巡らす、照明設備を整えるなど設備面の充実が重要です。また、敷地内に番犬を放し飼いにするなどは、犯人に対する心理的抑制効果があると思われます。特に、日頃から住居の周囲に侵入手段の足場となる樹木等がないか点検し、それを除去しておくことが重要です。
また、集合住宅の場合は、扉を開けて直接訪問者と対面しなくて済むように、カメラ付インターホンを設置する、玄関扉を堅牢な物にする等の配慮が必要です。最近では、警備会社による各種防犯機器を設置した機械警備システムが導入されている施設も増えてきています。
○ 警備保障会社の利用
警備保障会社と契約することも、防犯対策の1つの方法です。当国では警察が十分に機能していない状況にありますので利用する価値は高いと思われます。
○ ドア及び施錠関係
ドアは出来るだけ堅牢な物で二重ロックとし、相手が誰かを確認できるようにドアスコープを付ける必要があります。また、外出時、就寝時等には必ずドアや窓等の施錠も確認して下さい。
○ アパート選びのポイント
まず、道路と敷地内は開閉式の門で仕切られており、24時間体制で警備員による警備が行われているアパートを選ぶことが賢明です。次に、ほかの住人は先進国の外国人であることが好ましく、3階以上に居住することをお勧めします。これはマラリア蚊対策にもなります。さらに、火事等の緊急避難時に使用できる階段の有無を確認し、電気、水道等の各種トラブルに適切に対応できるかどうかを前もって確認しておく必要があります。
○ 現金、貴重品等の保管
万が一侵入等被害に遭った場合に備えて現金、貴重品等は、出来る限り分散して保管しましょう。
○ 居住態度
当地の気候を満喫し窓やドアを開けて開放的な雰囲気で生活することは非常に気持ちよいことですが、現在の当国事情を鑑みると、必ずしも生活態度として好ましいとは言い難いものがあります。住居の中を外部から見える状況にしておきますと、家の中の家具調度品等の設置状況だけでなく、家族構成や貴重品等を保管する状況をも窺われる恐れもありますので、常時周囲の状況に注意を払いながら、カーテンを締め切り、生活実態を外部から分からせないような工夫が必要です。また、家の出入りの際には周囲に不審者がいないかどうかなど、日頃から警戒することが犯罪予防につながります。
(2)外出時の注意事項
○ 大金等を所持しない
当国の強盗・窃盗犯人の特徴の1つは、被害者の持ち物などを徹底的に検査するということです。例えば、上着、ズボンのポケットは言うに及ばすパンツ、靴下の中に至るまでも執拗に探しますので、体のどこかに隠し通すということは不可能と思った方が賢明です。抵抗さえしなければ生命に対する危険は低いと思われますので、最初から大金を所持しないことが重要です。
○ 所持品は身から離さない
人混み等では、思わぬ油断からひったくり、置引き等の被害に遭うことがありますのでバック等の所持品は身から常に離さず持ち歩くことが重要です。
○ 単独外出は控える
一般犯罪の被害者を見ると、圧倒的多数はひとりでいるときに被害に遭っており、できる限り単独での外出は避けましょう。ただし、集団で路上を徒歩で移動すると、集会防止のためとして、警察から不当に拘束されるケースもありますので、基本的に徒歩での外出はお控えください。
○ 目的地までの車両利用
昼夜に限らずできる限り車両を利用して下さい。
○ 道路の選択
車両利用の場合でも、ある程度人通りがあり、なおかつ道幅が広いところを通るようにして下さい。緊急時に大声で周囲に助けを求めることが出来るものと考えられます。予め幾つかのルートを選択しておくのも良いかと思います。
○ 危険と思われる地域には近づかない
興味本位で近づかないようにすることが重要です。自ら進んで犯罪の被害に遭遇するようなことは止めて下さい。
○ 夜間における行動等
夜間においては、特に注意が必要となります。当国では、街路灯等が整備されておりませんので、非常に暗い場所が数多くあります。夜陰に紛れて何処に犯人が潜んでいるのか、判別し難いのが現実です。また、帰宅途中に尾行されているケースもありますので、夜間における行動は注意の上にも注意が必要です。
4.テロ・誘拐対策
東部(イツリ州、北キブ州、南キブ州)、カサイ3州(カサイ州、中央カサイ州、東カサイ州)、バ=ズエレ州北部、オー=ウエレ州などを中心にテロ・誘拐等が断続的に発生しています。これらの地域には渡航しないでください。
邦人の方が、万が一テロ・誘拐被害に遭った場合は直ぐに日本大使館にご連絡下さい。事件処理の第一義的責任は、コンゴ(民)当局にありますが、当大使館といたしましては、被害に遭われた方を一刻も早く安全に救出するために、当国政府、関係当局に対し最大限の対応を要請します。
5.交通事情
当国における交通事情は、とにかく公共の移動手段が乏しいと言う点に尽きます。鉄道はほとんど機能しておりませんし、公共輸送機関であるバスも台数が少なく、安全面からも利用は避けるべきです。
交通量は非常に多く、都市部では渋滞が常態化しています。交通法規は存在しますが、実質的には機能しておらず、法規を守らない者、交通マナーの悪い者が多いのが現状です。飲酒運転、信号無視、無灯火運転、整備不良、過積載車等の交通違反が横行しています。道路状態も一部を除けば穴だらけで補修されておらず、道路標識や車線区別もありません。
したがって、基本的に、ご自分で運転をしないことを強く推奨します。
なお、当国はジュネーブ条約締約国ですので、国際免許証で運転は可能です(日本の免許証、自動車車両登録証(カルト・ローズ)、自動車保険証とともに携行すること)。
6.事故防止対策
当国においては、右側通行であるという点を除けば基本的に交通ルールが存在しないと思って差し支えない現状です。万が一、人身事故を起こした場合は、周囲の者からのリンチを避けるため一旦その場を去って日本大使館に通報することを助言します。事情を知らない周囲の者は、事故原因がどうであれ、現地国民に肩入れし、暴力行為に及ぶことが常であるからです。また、老朽化した車両が多く走行しており、走行中にタイヤが外れるもの、ドアが突然開くもの、突然止まるもの等があるため、車間距離を十分取り、できるだけ併走しないよう心掛けて下さい。特に、夜間においては無灯火、片側灯火の車両があることから十分な注意が必要です。車両の保険もありますが、保険を掛けている車はほとんどないため、事故の際に相手に賠償金の請求を求めることは困難な場合がほとんどです。
7.緊急連絡先
大使館代表電話:
+243 (0)81 555 4731
+243 (0)81 555 4732
+243 (0)81 555 4733
+243 (0)81 555 4734
領事班:
+243 (0)81 880 5059
警察(緊急)112
警察(交通)099 823 5628(キンシャサ)
消防 099 936 9936(キンシャサ火災出動部隊)
病院・救急車 0898950300(キンシャサ)